プカプカ [70年代クロニクルズ]
1974年頃「気まぐれ飛行船」という深夜放送のラジオ番組がありました。
月曜の深夜1時~3時という時間帯だったが
安物のトランジスタラジオから聞こえてくるこの番組を、私は毎週楽しみにしていました。
パーソナリティは作家の片岡義男とジャズシンガーの安田南。
このふたりの、気まぐれで、もの静かで、思慮深い会話がなんとも魅力的でした。
当時、片岡義男が、雑誌「宝島」の編集長をしていることは知っていたが
安田南という女性がどんな人なのかは、まったく知らなかった。
ただ、ラジオから聴こえてくる彼女の繊細な声と柔らかな話し方、ノンシャランな雰囲気に
私は格別なものを感じていたのです。
番組はその後何年も続いていたが、私もいつしか深夜放送を聴かなくなっていました。
だいぶ経ってから、西岡恭蔵の名曲「プカプカ」のモデルが安田南であることを知りました。
彼女は、かなりのヘビースモーカーだったようで、1日に缶ピース100本ぐらい吸っていたとか。
あらためてこの曲を聴くと、自分が安田南に惹かれた理由が何となく分かるような気がしました。
この曲を聴くたび、私はあの時代の安田南のことを思い出します。

「プカプカ」は、多くの人たちにカバーされています。
原田芳雄、坂崎幸之助、大塚まさじ、泉谷しげる、宇崎竜童、高田渡、山崎ハコ、森山直太朗
桑田佳祐、つじあやの、福山雅治、かまやつひろし、夏川結衣、桃井かおり、中村雅俊…
月曜の深夜1時~3時という時間帯だったが
安物のトランジスタラジオから聞こえてくるこの番組を、私は毎週楽しみにしていました。
パーソナリティは作家の片岡義男とジャズシンガーの安田南。
このふたりの、気まぐれで、もの静かで、思慮深い会話がなんとも魅力的でした。
当時、片岡義男が、雑誌「宝島」の編集長をしていることは知っていたが
安田南という女性がどんな人なのかは、まったく知らなかった。
ただ、ラジオから聴こえてくる彼女の繊細な声と柔らかな話し方、ノンシャランな雰囲気に
私は格別なものを感じていたのです。
番組はその後何年も続いていたが、私もいつしか深夜放送を聴かなくなっていました。
だいぶ経ってから、西岡恭蔵の名曲「プカプカ」のモデルが安田南であることを知りました。
彼女は、かなりのヘビースモーカーだったようで、1日に缶ピース100本ぐらい吸っていたとか。
あらためてこの曲を聴くと、自分が安田南に惹かれた理由が何となく分かるような気がしました。
この曲を聴くたび、私はあの時代の安田南のことを思い出します。

「プカプカ」は、多くの人たちにカバーされています。
原田芳雄、坂崎幸之助、大塚まさじ、泉谷しげる、宇崎竜童、高田渡、山崎ハコ、森山直太朗
桑田佳祐、つじあやの、福山雅治、かまやつひろし、夏川結衣、桃井かおり、中村雅俊…
山口百恵は菩薩である [70年代クロニクルズ]
「山口百恵は菩薩である」
1979年に、平岡正明氏が書いた山口百恵の評論集のタイトルです。

私は、リアルタイムで山口百恵のヒット曲を知っていますが
現役時代の彼女の熱心なファンだったわけではありません。
後に、文庫になったこの本を読んだはずですが、内容も忘れてしまいました。
あの頃の歌謡曲は、自分の意志で聴くというより、自然に聴こえてくる音楽だったし
好き嫌いにかかわらず身体に沁みこんでくるものでした。
彼女が1980年に、21歳で芸能界を引退した後も、とくに関心があったわけではありません。
ただ「菩薩」という言葉が、山口百恵に対する形容詞のひとつとして浸透していることは
なんとなく知っていました。
最近「ザ・ベストテン 山口百恵 完全保存版」というDVDを観る機会があり
歌手としても女性としても、とても深いところを持った彼女の魅力に気づくことができました。

大人の女をイメージして、宇崎竜童と阿木曜子が作っていた頃の唄は、本当に凄いですね。
21歳の彼女の気品と風格は言葉を失うほどで、まさに仏像のような美しさに魅了されました。
当時の私は、山口百恵のそういう魅力に、まったく気づいていませんでした。
平岡正明氏が、本一冊分の文章を費やして語りたかった理由が
今になって、やっとわかったような気がします。
1度だけ、夜のテレビ局の駐車場で、山口百恵の姿を見かけたことがあります。
彼女は、駐車したクルマの後部座席でルームライトを点けて、本を読んでいました。
時間より早くテレビ局に到着し、控室に入る前の時間を過ごしていたのでしょう。
ルームライトの下に浮かび上がった彼女の横顔を見ただけですが
他のアイドルたちとは違う透き通ったオーラがありました。
1979年に、平岡正明氏が書いた山口百恵の評論集のタイトルです。

私は、リアルタイムで山口百恵のヒット曲を知っていますが
現役時代の彼女の熱心なファンだったわけではありません。
後に、文庫になったこの本を読んだはずですが、内容も忘れてしまいました。
あの頃の歌謡曲は、自分の意志で聴くというより、自然に聴こえてくる音楽だったし
好き嫌いにかかわらず身体に沁みこんでくるものでした。
彼女が1980年に、21歳で芸能界を引退した後も、とくに関心があったわけではありません。
ただ「菩薩」という言葉が、山口百恵に対する形容詞のひとつとして浸透していることは
なんとなく知っていました。
最近「ザ・ベストテン 山口百恵 完全保存版」というDVDを観る機会があり
歌手としても女性としても、とても深いところを持った彼女の魅力に気づくことができました。

大人の女をイメージして、宇崎竜童と阿木曜子が作っていた頃の唄は、本当に凄いですね。
21歳の彼女の気品と風格は言葉を失うほどで、まさに仏像のような美しさに魅了されました。
当時の私は、山口百恵のそういう魅力に、まったく気づいていませんでした。
平岡正明氏が、本一冊分の文章を費やして語りたかった理由が
今になって、やっとわかったような気がします。
1度だけ、夜のテレビ局の駐車場で、山口百恵の姿を見かけたことがあります。
彼女は、駐車したクルマの後部座席でルームライトを点けて、本を読んでいました。
時間より早くテレビ局に到着し、控室に入る前の時間を過ごしていたのでしょう。
ルームライトの下に浮かび上がった彼女の横顔を見ただけですが
他のアイドルたちとは違う透き通ったオーラがありました。
のこされた翼 [70年代クロニクルズ]
海岸には、海の家が立ち始めました。
今年もそろそろ、海の家の手伝いをする季節です。
かつては数10軒立ち並んだ海の家も、今では3軒に減ってしまいました。
1976年、その海岸を舞台に、大学の卒業制作として映画の制作をしました。

題名:「のこされた翼」40min 16mm
出演:飯山弘章 引地薫 藤原強 純アリス ほか
海辺の田舎町で暮らす高校生たちの夢と挫折を描いた40分のモノクロ映画です。
当初は、ピーター・ボグダノビッチの「ラストショー」という映画が念頭にあって
海辺の映画館に集まる高校生の話を考えていたのですが
映画館での撮影許可が難しく、違う物語に変更しました。


撮影は7月10日~20日までの10日間で、キャンプ場で合宿しながら撮影をしました。
学生映画といっても、映画を制作するには、かなりのお金がかかります。
機材、現像、編集、アフレコ、ダビング、プリント作業などは学校の施設が無料で使えますが
フィルム代、交通費、車両費、衣装費、美術費、雑費などの実費が発生します。
この作品の場合は、それらの費用が50万円ぐらいかかったと思います。
その費用は、監督、キャメラマン、俳優などが出し合います。
費用を出し合うことで、各自が卒業制作にエントリーするわけです。
監督は演出力、キャメラマンは撮影技術、演技者は演技力が、卒業制作の審査対象になります。
何の実績もない学生監督に自分の卒業を託すことになるので
スタッフや出演者は、作品を慎重に選定します。
4年の時は、制作費稼ぎのアルバイト、シナリオ執筆、準備、撮影、友人の撮影の手伝いなど
学生時代で、もっとも忙しい年になりました。
毎日学校に行っても、授業には出ず、いろいろな作業をしなければなりません。
そのため、教養過程などで単位を落としていると、卒業そのものが危うくなってきます。
実際、私もギリギリの単位での卒業でした。
当時の映画界は斜陽の風が吹いていて、卒業しても映画界に進めるかどうかは判りません。
これが、自分にとって最後の映画制作になるかもしれない、という思いもあり
どの学生たちも卒業制作には気合が入っていました。


長い間、私はこの作品を人に見せることができませんでした。
ああすればよかった、こうすればよかった、そんな後悔と言い訳が先に立ち
冷静に観ることができなかったからです。
しかし、40年近く経った今では、それが、自分の実力だと納得し
あの頃の自分の未熟さと精一杯さを、懐かしく思うことができるようになりました。

映画のラストシーンでの主人公のモノローグ。
「秋になれば、僕の手製のグライダーが
小さな夢を海の向こうまで運んでくれるにちがいない。
涙ぐみながら、僕はやっぱり小さな夢を捨てきれないのだと思う。
さよならを言うには、夏はあまりにもまぶしく輝いている」
※画質、音質ともかなり劣化してます。
今年もそろそろ、海の家の手伝いをする季節です。
かつては数10軒立ち並んだ海の家も、今では3軒に減ってしまいました。
1976年、その海岸を舞台に、大学の卒業制作として映画の制作をしました。

題名:「のこされた翼」40min 16mm
出演:飯山弘章 引地薫 藤原強 純アリス ほか
海辺の田舎町で暮らす高校生たちの夢と挫折を描いた40分のモノクロ映画です。
当初は、ピーター・ボグダノビッチの「ラストショー」という映画が念頭にあって
海辺の映画館に集まる高校生の話を考えていたのですが
映画館での撮影許可が難しく、違う物語に変更しました。


撮影は7月10日~20日までの10日間で、キャンプ場で合宿しながら撮影をしました。
学生映画といっても、映画を制作するには、かなりのお金がかかります。
機材、現像、編集、アフレコ、ダビング、プリント作業などは学校の施設が無料で使えますが
フィルム代、交通費、車両費、衣装費、美術費、雑費などの実費が発生します。
この作品の場合は、それらの費用が50万円ぐらいかかったと思います。
その費用は、監督、キャメラマン、俳優などが出し合います。
費用を出し合うことで、各自が卒業制作にエントリーするわけです。
監督は演出力、キャメラマンは撮影技術、演技者は演技力が、卒業制作の審査対象になります。
何の実績もない学生監督に自分の卒業を託すことになるので
スタッフや出演者は、作品を慎重に選定します。
4年の時は、制作費稼ぎのアルバイト、シナリオ執筆、準備、撮影、友人の撮影の手伝いなど
学生時代で、もっとも忙しい年になりました。
毎日学校に行っても、授業には出ず、いろいろな作業をしなければなりません。
そのため、教養過程などで単位を落としていると、卒業そのものが危うくなってきます。
実際、私もギリギリの単位での卒業でした。
当時の映画界は斜陽の風が吹いていて、卒業しても映画界に進めるかどうかは判りません。
これが、自分にとって最後の映画制作になるかもしれない、という思いもあり
どの学生たちも卒業制作には気合が入っていました。


長い間、私はこの作品を人に見せることができませんでした。
ああすればよかった、こうすればよかった、そんな後悔と言い訳が先に立ち
冷静に観ることができなかったからです。
しかし、40年近く経った今では、それが、自分の実力だと納得し
あの頃の自分の未熟さと精一杯さを、懐かしく思うことができるようになりました。

映画のラストシーンでの主人公のモノローグ。
「秋になれば、僕の手製のグライダーが
小さな夢を海の向こうまで運んでくれるにちがいない。
涙ぐみながら、僕はやっぱり小さな夢を捨てきれないのだと思う。
さよならを言うには、夏はあまりにもまぶしく輝いている」
※画質、音質ともかなり劣化してます。
タグ:のこされた翼 卒業制作
WHOLE EARTH CATALOG [70年代クロニクルズ]
「Made in USA catalog」は、アメリカのライフスタイルを伝えたムック本で
1975年、読売新聞から刊行されました。

翌年の1976年には続編の「Made in USA-2 Scrapbook of America」が刊行されました。
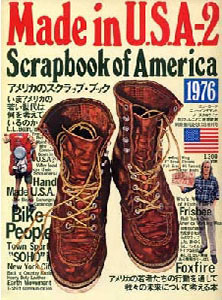
誌面には、70年代アメリカの自然志向なライフスタイルとともに
アウトドアに必要な道具や衣服が、たくさん掲載されていた。
私は、山登りやキャンプをしたことはなかったが
寝袋やテント、ナイフ、携帯コンロなど、様々な道具を眺めているだけでわくわくしたものです。
そして、機能性が高くて耐久性に優れているという意味の
「ヘビーデューティー」という言葉を知ったのも、たしかこの本でした。
Leeの101ジーンズ。
RED WINGのワークブーツ。
NORH FACEのマウンテンパーカ。
HUNTING WORLDのショルダーバッグ…
当時の私に買えるものは何もなかったけど
70年代の日本の若者のファッションに「ヘビーデューティ」という言葉が与えた影響は
とても大きかったように思います。
この本は、1968年にアメリカで創刊された
「WHOLE EARTH CATALOG」という雑誌の影響を受けて発刊されたのだろうと思います。
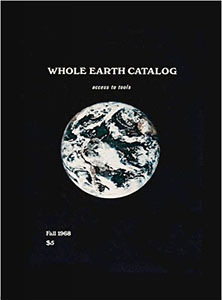
「WHOLE EARTH CATALOG」は、60~70年代のアメリカの若者たちの自立支援を目的として
発刊され、ヒッピー・カルチャーにも大きな影響を与えた雑誌です。
当時のアメリカの若者たちは、経済社会や管理社会の中での生活を拒否し
自然回帰的なライフスタイルを志向する傾向がありました。
彼らは大学や仕事を辞め、国内を放浪し、流れ着いた場所でコミューン(共同体)を作り
自給自足の生活を営もうとしていたのです。
いわゆるヒッピーです。
しかし、相当な知識やノウハウを知らないと、いきなり自給自足生活をすることはできません。
「WHOLE EARTH CATALOG」は、そういう生活をするための情報や
そこで暮らしていくための道具が、どこで手に入るのかなどについて書かれた雑誌でした。
お金で買えるもの以外に、自然エネルギーの活用、工芸、コミュニティ、遊牧生活、有機栽培
禅、ヨガ、東洋哲学…そういう情報が、カテゴリーごとに網羅されていました。
それらの情報が、カタログという形式で書かれていることが新鮮でした。
この雑誌を見せてもらったのは、ジャズ喫茶でアルバイトしていた同じ高校の女の子でした。
詳しい内容は理解できなかったけど、新しい生き方、新しい未来、新しい希望のようなことを
彼女は熱っぽく語っていたのを憶えています。
以前の記事にも書いたように、彼女はその後、高校を辞め、アメリカに渡って
ジャズミュージシャンのファラオ・サンダースの妻になりました。
私が今でも、ヒッピーやコミューンに関心があり、自給野菜にこだわっているのも
高校生の時、彼女が見せてくれた「WHOLE EARTH CATALOG」の影響だと思ったりもします。
とは言え、今の私は、101ジーンズが、ユニクロのイージーパンツに変わり
ワークブーツが、ホームセンターのゴム長に変わり
マウンテンパーカが、ワークマンの作業着に変わっています。
「ヘビーデューティ」であることは大事な要素ですが、安価であること、という条件が加わりました。
1975年、読売新聞から刊行されました。

翌年の1976年には続編の「Made in USA-2 Scrapbook of America」が刊行されました。
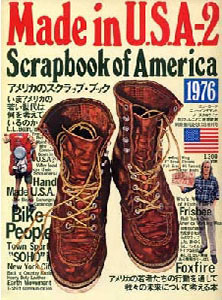
誌面には、70年代アメリカの自然志向なライフスタイルとともに
アウトドアに必要な道具や衣服が、たくさん掲載されていた。
私は、山登りやキャンプをしたことはなかったが
寝袋やテント、ナイフ、携帯コンロなど、様々な道具を眺めているだけでわくわくしたものです。
そして、機能性が高くて耐久性に優れているという意味の
「ヘビーデューティー」という言葉を知ったのも、たしかこの本でした。
Leeの101ジーンズ。
RED WINGのワークブーツ。
NORH FACEのマウンテンパーカ。
HUNTING WORLDのショルダーバッグ…
当時の私に買えるものは何もなかったけど
70年代の日本の若者のファッションに「ヘビーデューティ」という言葉が与えた影響は
とても大きかったように思います。
この本は、1968年にアメリカで創刊された
「WHOLE EARTH CATALOG」という雑誌の影響を受けて発刊されたのだろうと思います。
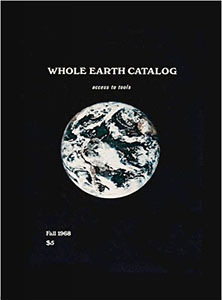
「WHOLE EARTH CATALOG」は、60~70年代のアメリカの若者たちの自立支援を目的として
発刊され、ヒッピー・カルチャーにも大きな影響を与えた雑誌です。
当時のアメリカの若者たちは、経済社会や管理社会の中での生活を拒否し
自然回帰的なライフスタイルを志向する傾向がありました。
彼らは大学や仕事を辞め、国内を放浪し、流れ着いた場所でコミューン(共同体)を作り
自給自足の生活を営もうとしていたのです。
いわゆるヒッピーです。
しかし、相当な知識やノウハウを知らないと、いきなり自給自足生活をすることはできません。
「WHOLE EARTH CATALOG」は、そういう生活をするための情報や
そこで暮らしていくための道具が、どこで手に入るのかなどについて書かれた雑誌でした。
お金で買えるもの以外に、自然エネルギーの活用、工芸、コミュニティ、遊牧生活、有機栽培
禅、ヨガ、東洋哲学…そういう情報が、カテゴリーごとに網羅されていました。
それらの情報が、カタログという形式で書かれていることが新鮮でした。
この雑誌を見せてもらったのは、ジャズ喫茶でアルバイトしていた同じ高校の女の子でした。
詳しい内容は理解できなかったけど、新しい生き方、新しい未来、新しい希望のようなことを
彼女は熱っぽく語っていたのを憶えています。
以前の記事にも書いたように、彼女はその後、高校を辞め、アメリカに渡って
ジャズミュージシャンのファラオ・サンダースの妻になりました。
私が今でも、ヒッピーやコミューンに関心があり、自給野菜にこだわっているのも
高校生の時、彼女が見せてくれた「WHOLE EARTH CATALOG」の影響だと思ったりもします。
とは言え、今の私は、101ジーンズが、ユニクロのイージーパンツに変わり
ワークブーツが、ホームセンターのゴム長に変わり
マウンテンパーカが、ワークマンの作業着に変わっています。
「ヘビーデューティ」であることは大事な要素ですが、安価であること、という条件が加わりました。
色街 [70年代クロニクルズ]
向島の「鳩の街」を撮影していた2kさんの写真に刺激され
かつて私娼街があった水戸の裏町を散策しました。
今回散策した水戸の奈良屋町は、間口の狭い酒場が並んだ元カフェー街で
1940年代から1950年代半ばまで、私娼たちが店先に立って客を曳いていたようです。
現在は裏町の飲み屋街という印象しかありませんが
よく見るとかつての色街だったころの遺構を偲ぶことができます。

高校生の頃に、私はこの界隈をよく歩いていました。
当時は、すでに色街としての機能は終わっていたし、娼婦が客を曳く姿も見たことはありません。
ただ、どこかの引き戸が開いて緑魔子のような女が顔を出し、胸元に忍ばせたマッチで
私のタバコに火を点けてくれるようなことが起こらないだろうかなどと妄想したりしていました。
緑魔子主演 映画「やさしいにっぽん人」より

当時の私にも、娼婦が何をしている女なのかは、朧げにわかっていたし
そんなことを考えるたび、激しく動悸した憶えもあります。
映画のオープンセットのような作り物めいたカフェー街の景色に惹かれ
この界隈を舞台に、8㎜の自主映画を撮影したりもしていた。

数年後、上京した私が驚いたことは、リアルな私娼街が東京にはまだ存在していたことでした。
新宿東南口の甲州街道下のヌードスタジオのあった路地や
同じく新宿二丁目の路地には、私娼窟がいくつか残っていました。
まるでアングラ演劇のような灯りのともる路地を、私は胸をときめかせながら歩きました。
横浜日ノ出町のガード下、沖縄の真栄原などは、数年前にその姿を消しているが
川崎の堀之内や大阪の飛田新地などは、表向きは飲食店を標榜していても
実態は私娼街として今でも営業しているようです。
今でも日本中に、私娼街は数えきれないほどあるのだろう。
役所は、そういうエリアを商業地域やアートの街として再開発させたいのでしょうが
色街として歩んできた街や土地の歴史は簡単に消せるはずもないと思います。
正月の水戸奈良屋町を歩きながら、私は高校時代の幼い妄想を久しぶりに思い出していました。
しかし、私のタバコに火を点けてくれるような裏町の女は、やはり現れませんでした。
"
かつて私娼街があった水戸の裏町を散策しました。
今回散策した水戸の奈良屋町は、間口の狭い酒場が並んだ元カフェー街で
1940年代から1950年代半ばまで、私娼たちが店先に立って客を曳いていたようです。
現在は裏町の飲み屋街という印象しかありませんが
よく見るとかつての色街だったころの遺構を偲ぶことができます。
高校生の頃に、私はこの界隈をよく歩いていました。
当時は、すでに色街としての機能は終わっていたし、娼婦が客を曳く姿も見たことはありません。
ただ、どこかの引き戸が開いて緑魔子のような女が顔を出し、胸元に忍ばせたマッチで
私のタバコに火を点けてくれるようなことが起こらないだろうかなどと妄想したりしていました。
緑魔子主演 映画「やさしいにっぽん人」より

当時の私にも、娼婦が何をしている女なのかは、朧げにわかっていたし
そんなことを考えるたび、激しく動悸した憶えもあります。
映画のオープンセットのような作り物めいたカフェー街の景色に惹かれ
この界隈を舞台に、8㎜の自主映画を撮影したりもしていた。
数年後、上京した私が驚いたことは、リアルな私娼街が東京にはまだ存在していたことでした。
新宿東南口の甲州街道下のヌードスタジオのあった路地や
同じく新宿二丁目の路地には、私娼窟がいくつか残っていました。
まるでアングラ演劇のような灯りのともる路地を、私は胸をときめかせながら歩きました。
横浜日ノ出町のガード下、沖縄の真栄原などは、数年前にその姿を消しているが
川崎の堀之内や大阪の飛田新地などは、表向きは飲食店を標榜していても
実態は私娼街として今でも営業しているようです。
今でも日本中に、私娼街は数えきれないほどあるのだろう。
役所は、そういうエリアを商業地域やアートの街として再開発させたいのでしょうが
色街として歩んできた街や土地の歴史は簡単に消せるはずもないと思います。
正月の水戸奈良屋町を歩きながら、私は高校時代の幼い妄想を久しぶりに思い出していました。
しかし、私のタバコに火を点けてくれるような裏町の女は、やはり現れませんでした。
"
ラブソング [70年代クロニクルズ]
ほとんどの唄はラブソングだと思う。
恋人に 会いたいと思う気持ち。
片想いの人を 切なく恋うる気持ち。
愛する人の そばにいたいと願う気持ち。
そんな気持ちに想いをめぐらす透明な瞬間に、ラブソングは生まれるのでしょう。
ふと聴いたその唄に自身を投影し、自分の恋愛を見つめることがあります。
思い浮かぶラブソングは、年代によって変わっていきましたが
僕にとって印象深いのは、やはり70年代の唄です。
ポリドール時代の井上陽水には、ラブソングの名曲がたくさんありました。


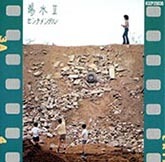
陽水と忌野清志郎の共作「帰れない二人」は、好きな唄のひとつです。
♪もう 星は帰ろうとしてる 帰れない二人を 残して~
この詩に、どうしようもなく感じ入ってしまいます。
恋人と、あてもなく歩いた春の夜。
夜道を足音の中で語り明かしたこと。
盗んだ自転車に、ふたり乗りして走り回ったこと。
「帰れない二人」を聴くと、落し物でも探すように、あの夜のことを想いだします。
恋人に 会いたいと思う気持ち。
片想いの人を 切なく恋うる気持ち。
愛する人の そばにいたいと願う気持ち。
そんな気持ちに想いをめぐらす透明な瞬間に、ラブソングは生まれるのでしょう。
ふと聴いたその唄に自身を投影し、自分の恋愛を見つめることがあります。
思い浮かぶラブソングは、年代によって変わっていきましたが
僕にとって印象深いのは、やはり70年代の唄です。
ポリドール時代の井上陽水には、ラブソングの名曲がたくさんありました。


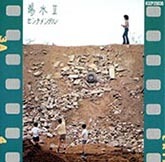
陽水と忌野清志郎の共作「帰れない二人」は、好きな唄のひとつです。
♪もう 星は帰ろうとしてる 帰れない二人を 残して~
この詩に、どうしようもなく感じ入ってしまいます。
恋人と、あてもなく歩いた春の夜。
夜道を足音の中で語り明かしたこと。
盗んだ自転車に、ふたり乗りして走り回ったこと。
「帰れない二人」を聴くと、落し物でも探すように、あの夜のことを想いだします。
マールトン・ホテル [70年代クロニクルズ]
1974年、7月。アルバイトで買った航空券を手に、ニューヨークへ行った。
イーストヴィレッジのラママシアターで公演する東京キッドブラザースの公演記録を
8㎜カメラで撮影するという目的があったからだ。
東由多加と関わりのある寺山修司のインタビューや、稽古シーンは既に撮り終えていたので
ニューヨークでは公演の様子を中心に劇団員たちの日常を撮る予定だった。
この旅には、結婚前の家内も同行していました。
JFK空港から乗ったバスでマンハッタンに入るとき
バスのカーラジオからサイモン&ガーファンクルの「アメリカ」が聴こえてきた。
何と言うタイミングだろうと思いながら、クイーンズボロ橋の向こうに見えるマンハッタンを眺めた。
到着した日は劇団員たちが宿泊しているロフトに泊めてもらうことにしたが
翌日からは、どこかの安宿を探さなければならなかった。
グリニッチ・ヴィレッジを探し回り、8丁目にあるマールトン・ホテルに投宿することにした。

部屋はまずまずの広さだが、トイレとシャワールームをその階の全室で共用するタイプでした。
宿代は1週間15ドル。当時は1ドル約300円ぐらい。
ワシントン広場とNYUの校舎が目と鼻の先にあるのに何故か安いホテルだった。
その理由はすぐに判明した。
マールトン・ホテルは、ジャンキーや売春婦など、どう見てもクレイジーな人たちの巣窟だった。
「たしかにヤバい連中も住んでいる。しかし、彼らは同じねぐらの住人には手を出さない。
だから、ここはニューヨークで一番安全なホテルなんだ」
ホテルのフロントまで、そんなことを言っていた。
もっとも、他の住人にとっては僕もヤバそうな人間に見えたかもしれないが。
とりあえず1週間だけ様子をみようと、家内と一緒に荷物を運んだ。
「ウエストサイド物語」に出てくるような非常階段が興味を惹いた。

戸惑ったことは、エレベータで見知らぬ誰かと乗り合わせたり廊下で人とすれ違うとき
誰もが気安く声をかけてくることでした。
そういう場面でのリアクションが、僕は得意ではありません。
東洋人の僕を見ると、ブルース・リーのカンフーポーズをしてみせる者もいた。
「マヂでビクっとなるから!そういうの禁止な!」
そんな英語の語彙は僕にはないので、ホテルの廊下で人とすれ違うと軽く緊張したものです。
数日滞在すると、ホテルの住人たちの中には顔馴染みもできました。
薄ら笑いを浮かべて話かけてくるニヒルな顔立ちの男が、僕たちと同じ階で暮らしていました。
彼は、いつもボソボソと小さい声で話すので、何を言っているのか分かりません。
ドラッグでも売りつけようとしているのかと思い、得体のしれない彼を胡散臭く感じていました。
その男が、のちにミッキー・ロークという名の映画俳優になるとは想像もしていませんでした。

東京キッドブラザースの2度目のニューヨーク公演「THE CITY」は幕が開き
ニューヨークタイムズなど有力誌の演劇評論家がぞくぞくと劇場にやってきた。
翌日の新聞に劇評が出ると、英語力のある劇団員が翻訳して皆に伝えた。
ニューヨークの演劇は、劇評によって天国と地獄に分かれる。
1970年、東京キッドブラザースが「THE GOLDEN BAT」を公演したときは好意的な劇評が出て
ラママシアターからオフ・ブロードウェイのシェリダンスクエア・プレイハウスに駆け上がった。
そして、7ヶ月に及ぶロングランを果たし、エド・サリバン・ショーにも出演した。
音楽監督の下田逸郎は、卓越した作曲家に与えられる「Drama Desk Award」を獲った。
高校生の時、そのことを美術雑誌で知ったことが、僕と東京キッドブラザースとの出会いだった。
しかし、1974年の「THE CITY」の劇評は芳しいものではなかった。
客入りも悪く、演出の東由多加は何度も芝居を作り変えていった。
ラママシアターは、イースト・ヴィレッジにある実験劇場で
ロバート・デニーロ、アル・パチーノ、サム・シェパード、ハーヴェイ・カイテルなどの
無名時代を支えた劇場としても知られている。

ラママシアター主宰のエレン・スチュワートは、2007年、高松宮殿下記念世界文化賞を受けた。

1992年、ラママシアターの経済的な困窮を救おうと慈善パーティが行われたことがある。
たまたまロケでニューヨークにいた僕は、100ドルの寄付金を持ってラママシアターに向かった。
パーティ会場にいた主催者は、ロバート・デニーロだった。
いつの間にか1ヶ月が過ぎ、もうすぐ9月になろうとしていた。
1週間のつもりで逗留したマールトンホテルに、僕たちは相変わらず滞在していた。

8月。東京キッドブラザースは、ニューヨークに見切りをつけ、ヨーロッパでの公演を調整していた。
劇団とともにロンドン公演へ行く者、そのままニューヨークに残る者、東京へ帰る者。
劇団員たちは決断を迫られ、何となくそわそわしていた。
それぞれが自分の可能性を模索していたように見えた。
あの時、自分が劇団員だったら、どういう選択をしていただろうかと思う。
9月。急に空が高くなり、季節が入れ替わった。ニューヨークの秋は早い。
もう少しだけニューヨークに留まりたくて、僕は8㎜カメラを手放すことにした。
14丁目の質屋に持っていくと150ドルで取ってくれた。
10月。東京キッドブラザースはロンドンへ向かい、僕たちは日本へ帰ることにした。
帰る日の朝、マールトン・ホテルのミッキー・ロークに「僕たち日本に帰るよ」と言うと
「See You」と言って、いつものように薄ら笑いを浮かべた。
マールトンホテルは、現在もニューヨークで営業を続けている。
1週間15ドルの安宿ではなく、1泊250ドルのブティックホテルとして。
ジャンキーも、売春婦も、ドラッグ売りも、ヒッピーも、ミッキー・ロークも、もう、そこにはいない。
イーストヴィレッジのラママシアターで公演する東京キッドブラザースの公演記録を
8㎜カメラで撮影するという目的があったからだ。
東由多加と関わりのある寺山修司のインタビューや、稽古シーンは既に撮り終えていたので
ニューヨークでは公演の様子を中心に劇団員たちの日常を撮る予定だった。
この旅には、結婚前の家内も同行していました。
JFK空港から乗ったバスでマンハッタンに入るとき
バスのカーラジオからサイモン&ガーファンクルの「アメリカ」が聴こえてきた。
何と言うタイミングだろうと思いながら、クイーンズボロ橋の向こうに見えるマンハッタンを眺めた。
到着した日は劇団員たちが宿泊しているロフトに泊めてもらうことにしたが
翌日からは、どこかの安宿を探さなければならなかった。
グリニッチ・ヴィレッジを探し回り、8丁目にあるマールトン・ホテルに投宿することにした。

部屋はまずまずの広さだが、トイレとシャワールームをその階の全室で共用するタイプでした。
宿代は1週間15ドル。当時は1ドル約300円ぐらい。
ワシントン広場とNYUの校舎が目と鼻の先にあるのに何故か安いホテルだった。
その理由はすぐに判明した。
マールトン・ホテルは、ジャンキーや売春婦など、どう見てもクレイジーな人たちの巣窟だった。
「たしかにヤバい連中も住んでいる。しかし、彼らは同じねぐらの住人には手を出さない。
だから、ここはニューヨークで一番安全なホテルなんだ」
ホテルのフロントまで、そんなことを言っていた。
もっとも、他の住人にとっては僕もヤバそうな人間に見えたかもしれないが。
とりあえず1週間だけ様子をみようと、家内と一緒に荷物を運んだ。
「ウエストサイド物語」に出てくるような非常階段が興味を惹いた。

戸惑ったことは、エレベータで見知らぬ誰かと乗り合わせたり廊下で人とすれ違うとき
誰もが気安く声をかけてくることでした。
そういう場面でのリアクションが、僕は得意ではありません。
東洋人の僕を見ると、ブルース・リーのカンフーポーズをしてみせる者もいた。
「マヂでビクっとなるから!そういうの禁止な!」
そんな英語の語彙は僕にはないので、ホテルの廊下で人とすれ違うと軽く緊張したものです。
数日滞在すると、ホテルの住人たちの中には顔馴染みもできました。
薄ら笑いを浮かべて話かけてくるニヒルな顔立ちの男が、僕たちと同じ階で暮らしていました。
彼は、いつもボソボソと小さい声で話すので、何を言っているのか分かりません。
ドラッグでも売りつけようとしているのかと思い、得体のしれない彼を胡散臭く感じていました。
その男が、のちにミッキー・ロークという名の映画俳優になるとは想像もしていませんでした。

東京キッドブラザースの2度目のニューヨーク公演「THE CITY」は幕が開き
ニューヨークタイムズなど有力誌の演劇評論家がぞくぞくと劇場にやってきた。
翌日の新聞に劇評が出ると、英語力のある劇団員が翻訳して皆に伝えた。
ニューヨークの演劇は、劇評によって天国と地獄に分かれる。
1970年、東京キッドブラザースが「THE GOLDEN BAT」を公演したときは好意的な劇評が出て
ラママシアターからオフ・ブロードウェイのシェリダンスクエア・プレイハウスに駆け上がった。
そして、7ヶ月に及ぶロングランを果たし、エド・サリバン・ショーにも出演した。
音楽監督の下田逸郎は、卓越した作曲家に与えられる「Drama Desk Award」を獲った。
高校生の時、そのことを美術雑誌で知ったことが、僕と東京キッドブラザースとの出会いだった。
しかし、1974年の「THE CITY」の劇評は芳しいものではなかった。
客入りも悪く、演出の東由多加は何度も芝居を作り変えていった。
ラママシアターは、イースト・ヴィレッジにある実験劇場で
ロバート・デニーロ、アル・パチーノ、サム・シェパード、ハーヴェイ・カイテルなどの
無名時代を支えた劇場としても知られている。

ラママシアター主宰のエレン・スチュワートは、2007年、高松宮殿下記念世界文化賞を受けた。

1992年、ラママシアターの経済的な困窮を救おうと慈善パーティが行われたことがある。
たまたまロケでニューヨークにいた僕は、100ドルの寄付金を持ってラママシアターに向かった。
パーティ会場にいた主催者は、ロバート・デニーロだった。
いつの間にか1ヶ月が過ぎ、もうすぐ9月になろうとしていた。
1週間のつもりで逗留したマールトンホテルに、僕たちは相変わらず滞在していた。

8月。東京キッドブラザースは、ニューヨークに見切りをつけ、ヨーロッパでの公演を調整していた。
劇団とともにロンドン公演へ行く者、そのままニューヨークに残る者、東京へ帰る者。
劇団員たちは決断を迫られ、何となくそわそわしていた。
それぞれが自分の可能性を模索していたように見えた。
あの時、自分が劇団員だったら、どういう選択をしていただろうかと思う。
9月。急に空が高くなり、季節が入れ替わった。ニューヨークの秋は早い。
もう少しだけニューヨークに留まりたくて、僕は8㎜カメラを手放すことにした。
14丁目の質屋に持っていくと150ドルで取ってくれた。
10月。東京キッドブラザースはロンドンへ向かい、僕たちは日本へ帰ることにした。
帰る日の朝、マールトン・ホテルのミッキー・ロークに「僕たち日本に帰るよ」と言うと
「See You」と言って、いつものように薄ら笑いを浮かべた。
マールトンホテルは、現在もニューヨークで営業を続けている。
1週間15ドルの安宿ではなく、1泊250ドルのブティックホテルとして。
ジャンキーも、売春婦も、ドラッグ売りも、ヒッピーも、ミッキー・ロークも、もう、そこにはいない。
アルバイト [70年代クロニクルズ]
学生時代に実家から毎月送られてくる現金書留には、いつも3万円が入っていました。
家賃と光熱費を払うと、手元に残るのは2万円。
食費とタバコ代の他、池袋の文芸坐に5~6回通うと、その2万円はキレイになくなりました。
カツカツだけど、何とか暮らしていける金額でした。
手持ちがなくなると、学食で30円のライスを注文し、七味と醤油をかけて昼食を済ませた。
学費や生活費を自分で稼ぐ猛者もいたから、自分は恵まれているほうだと思っていた。
しかし、仕送りだけでは本やレコードを買うことは難しく、時々短期のアルバイトをした。
当時のアルバイトの時給は330円~380円で、1日やれば2,500~3,000円ぐらいになった。
夜警のアルバイトは、もっと高額だったような気もする。
テレビの時代劇のエキストラもよくやった。
プロの撮影現場を見ることができると思って始めたのだが
エキストラは背景の置き物のような役割なので、いつもキャメラから遠いところに立たされた。
髪も長かったので、ヅラをつけてもらえず、ほっかむり姿で荷車を引いたり
大名行列のシーンで道端にしゃがみ込んで一日中土下座、そんなことばかりやらされた。

1974年の夏「東京キッドブラザース」は2度目のニューヨーク公演を計画していました。
その公演に随行するため、僕は渡航費を稼がなくてはならなかった。
羽田からニューヨークまでの格安往復航空券は25万円。
40年前の航空券の値段は今の3倍ぐらいしてました。
航空券代25万円と滞在費を10万円として、合計35万円を稼ぐにはどうすればいいのか。
1日に3つの仕事をかけもちする計画を立てた。
06時~09時:有楽町でオフィスビルの掃除。
10時~15時:神田の天ぷらやで洗い物と出前。
16時~23時:池袋の鰻屋でウェイター。
まあ、やれるだけ、やってみようと。
5時に江古田のアパートを出て、戻ってくるのは24時。
朝から夜中まで働いて、ひと月に13~14万円ぐらいの稼ぎだった。
辛かったのは、バイト先の休日がそれぞれ違うので、まる1日休める日がないことでした。
それでも、食事はアルバイト先で賄うことができたし
鰻屋では、仕事終わりにシャワーを使わせてもらっていたので、銭湯代も浮きました。
さらに、江古田~有楽町の定期があるので他のバイトの交通費を浮かすこともできた。
飲食のアルバイトの楽しみは、賄い料理です。
天ぷら屋の賄いは美味しくて、あっというまに平らげてしまい
さらにお替りしたご飯に、天かすをのせ丼つゆをかけて食べていた。
鰻屋も同じで、お替りしたごはんに売れ残りの兜焼きや肝焼きをのせ
うな丼の丼つゆをかけて食べた。
2月~4月までの3ヶ月間、僕はそれらのバイトに没頭した。
目標額の35万円分の仕事を終えた時、すべてのバイトを辞めました。
7月、先に行った劇団員たちを追いかけて、僕はニューヨークへ出発した。
いろんなアルバイトをやりましたが、3つの仕事をかけもちしたのは最初で最後でした。
お金はなかったけれど、それが普通だったし貧乏だとも思っていなかった。
過ぎ去った時代は美しく見えるのかもしれないが
僕にとっての70年代は、無邪気で、清々しくて、自由な空気に満ちていた。
何よりも、希望があった。
家賃と光熱費を払うと、手元に残るのは2万円。
食費とタバコ代の他、池袋の文芸坐に5~6回通うと、その2万円はキレイになくなりました。
カツカツだけど、何とか暮らしていける金額でした。
手持ちがなくなると、学食で30円のライスを注文し、七味と醤油をかけて昼食を済ませた。
学費や生活費を自分で稼ぐ猛者もいたから、自分は恵まれているほうだと思っていた。
しかし、仕送りだけでは本やレコードを買うことは難しく、時々短期のアルバイトをした。
当時のアルバイトの時給は330円~380円で、1日やれば2,500~3,000円ぐらいになった。
夜警のアルバイトは、もっと高額だったような気もする。
テレビの時代劇のエキストラもよくやった。
プロの撮影現場を見ることができると思って始めたのだが
エキストラは背景の置き物のような役割なので、いつもキャメラから遠いところに立たされた。
髪も長かったので、ヅラをつけてもらえず、ほっかむり姿で荷車を引いたり
大名行列のシーンで道端にしゃがみ込んで一日中土下座、そんなことばかりやらされた。

1974年の夏「東京キッドブラザース」は2度目のニューヨーク公演を計画していました。
その公演に随行するため、僕は渡航費を稼がなくてはならなかった。
羽田からニューヨークまでの格安往復航空券は25万円。
40年前の航空券の値段は今の3倍ぐらいしてました。
航空券代25万円と滞在費を10万円として、合計35万円を稼ぐにはどうすればいいのか。
1日に3つの仕事をかけもちする計画を立てた。
06時~09時:有楽町でオフィスビルの掃除。
10時~15時:神田の天ぷらやで洗い物と出前。
16時~23時:池袋の鰻屋でウェイター。
まあ、やれるだけ、やってみようと。
5時に江古田のアパートを出て、戻ってくるのは24時。
朝から夜中まで働いて、ひと月に13~14万円ぐらいの稼ぎだった。
辛かったのは、バイト先の休日がそれぞれ違うので、まる1日休める日がないことでした。
それでも、食事はアルバイト先で賄うことができたし
鰻屋では、仕事終わりにシャワーを使わせてもらっていたので、銭湯代も浮きました。
さらに、江古田~有楽町の定期があるので他のバイトの交通費を浮かすこともできた。
飲食のアルバイトの楽しみは、賄い料理です。
天ぷら屋の賄いは美味しくて、あっというまに平らげてしまい
さらにお替りしたご飯に、天かすをのせ丼つゆをかけて食べていた。
鰻屋も同じで、お替りしたごはんに売れ残りの兜焼きや肝焼きをのせ
うな丼の丼つゆをかけて食べた。
2月~4月までの3ヶ月間、僕はそれらのバイトに没頭した。
目標額の35万円分の仕事を終えた時、すべてのバイトを辞めました。
7月、先に行った劇団員たちを追いかけて、僕はニューヨークへ出発した。
いろんなアルバイトをやりましたが、3つの仕事をかけもちしたのは最初で最後でした。
お金はなかったけれど、それが普通だったし貧乏だとも思っていなかった。
過ぎ去った時代は美しく見えるのかもしれないが
僕にとっての70年代は、無邪気で、清々しくて、自由な空気に満ちていた。
何よりも、希望があった。
ジャズ喫茶 [70年代クロニクルズ]

熱心なジャズファンでもないのに、ジャズ喫茶にはよく通った。
70年代、水戸には数軒のジャズ喫茶があった。
水戸駅近くにあった「S&F」という店は、昼の12時頃から店を開けていたので
時々、学校をサボって昼間からその店で時間をつぶすことがあった。
「S&F」は私語厳禁のストイックなジャズ喫茶ではなく、いつも適度な客のざわめきに満ちていた。
タバコをおぼえたのも、その店だった。
当時の喫茶店でコーヒーを注文すると、80円~100円ぐらいだったが「S&F」は150円もした。
50円はレコード代だよ、と客の誰かが教えてくれた。
店には、ビル・エヴァンスやコルトレーンなんかが流れ
本棚には「スイングジャーナル」「現代詩手帳」「美術手帳」が並んでいた。
夕方からの映画館のバイトのあとで、もう一度「S&F」に行くこともあった。
夜は、ジャズヴォーカル中心の選曲になり、酒も出すので店の雰囲気は少し変わる。
「S&F」に行くようになったのは、同じ高校の女の子が、その店のことをよく話していたからだ。
彼女とはクラスは違うが、レコードの貸し借りのようなことを2~3度やったことがあった。
僕と同じ年とは思えないほど早熟な女の子で、フランソワーズ・サガンやサリンジャーを愛読し
アメリカで発刊された「WHOLE EARTH CATALOG」のことなどを教えてくれた。
とがった顎と薄情そうな唇が、とても大人びて見えた。
彼女の話を聞いていると、世の中のことを何も知らない自分が痛々しく思えた。
高校2年の秋、彼女は突然退学してしまった。
彼女と仲のよかった友人に聞いても、消息を知るものは誰もいなかった。
彼女とは、それっきりだった。
付き合っていたわけではないけど、とても気になる存在だった。
ある日、彼女が話していた「S&F」を訪ねてみた。
狭い階段を上がった2階にその店はあり、入口の頑丈な木製のドアはどこか威圧感があって
入るのをためらうほどだった。
薄暗い店内は現実と隔絶された隠れ家のような雰囲気で
彼女の言っていた「スゴクいい」の意味が分かるような気がした。
それがきっかけで僕は「S&F」に行くようになった。
やがて僕も東京で暮らすようになり、たまにジャズ喫茶に行くと彼女のことを思い出した。
新宿の「DUG」「DIG」吉祥寺の「OUTBACK」「Funky」横浜の「ちぐさ」
村上春樹が店主をしていた千駄ヶ谷の「ピーターキャット」…
社会人になると彼女のことを思い出すことはなくなっていた。
昨年、久しぶりに「S&F」に行ってみた。
40数年前と同じ場所にソニー・ロリンズのポスターが貼ってあり、店主も僕のことを憶えていた。
「昔、うちによく来てた女の子がファラオ・サンダースと結婚してニューヨークに住んでいる」
と、店主が言った。
ファラオ・サンダースは、コルトレーンの後継者と言われたNYのサックスプレーヤーだ。
話を聞くと、その女の子はやはり同じ高校の、あの彼女だった。
高校を辞め、東京でアルバイトをしてお金を貯め、NYへ渡ったらしい。
うまく言えないが、とても彼女らしいと思った。
高校を中退し、どんな思いでNYへ渡り、どんな人を愛し、どんな風に生きていたのだろう。
コルトレーンのバラッズを聴きながら、僕はぼんやりと、あの70年代のことを考える。
同窓会が終わって [70年代クロニクルズ]
7月7日、雨の七夕。
米軍ハウスの住人たちの36年ぶりの同窓会で東京へ。
結局シモンの連絡先は判らず、音楽家のオカモトさんも都合で来れず、
5人のメンバーでやることになった。
午後の早い時間に東京へ着いたので、新国立美術館でエルミタージュ美術館展へ行く。

マチスの「赤い部屋」を観てしまうと、約束の時間にはまだ時間があった。
歩こうか、と家内が言うので西麻布を抜けて渋谷まで歩く。
会場のスペイン料理レストランには少し早く着いた。
店が開いていなかったので、外で待っていると、
通りの向こうから金髪のKさんがやってきた。
彼女は、京都から来てくれた。
現在は書家として、レストランや料亭の筆文字ロゴを書いている。
NHKドラマの「ええにょぼ」などテレビの筆文字タイトルなんかも彼女の仕事だ。
間もなくTさんとIさんが、やってきた。
Tさんは、宇都宮で石のオブジェなどを創作している。
Iさんは、渋谷でデザイン事務所を立ち上げている。
このメンバーは個々に会うことはあったが、全員で会うのは初めてだった。
シャンパンで乾杯。
〈Kさんと家内だけ写真使用の許可が下りました〉

みんな、何を話していいか分からない。
36年ぶりだね、という言葉を何度も繰り返している。
何かきっかけがあれば記憶の糸がほぐれるのだろう、と思っていたが、
盛り上がるような昔話にはならず、みんな静かにワインを飲んでいる。
こういう感じ、どこかで見たことがあると思っていた。
「再会の時」というアメリカ映画だ。

60年代後半のアメリカのヒッピームーブメントの只中にいた仲間たちが、
友人の葬式で再会し、週末を過ごすという作品だ。
それにしても、僕と家内以外は、みんなつつましやかにしている。
熱い話をするには、もう少し時間が必要なのか、
それとも時間がたちすぎて、
振り返るべき過去なんてどうでもよくなってしまったのだろうか。
渋谷から西麻布へ流れた二次会でも、その空気は変わらなかった。
やがてシモンの話になった。
20年ほど前、シモンがTさんのいる宇都宮に会いに来たという。
長野のコミューンに行く途中で宇都宮に寄ったらしいが、
それ以来、連絡が途絶えたままであると。
シモンの話は、それ以上続かなかった。
夜更けの西麻布を5人で歩きながら、
近々、みんなで会おうという話をして僕たちは別れた。
米軍ハウスで一緒に暮らしていた岡本一生の歌を貼り付けます。
米軍ハウスの住人たちの36年ぶりの同窓会で東京へ。
結局シモンの連絡先は判らず、音楽家のオカモトさんも都合で来れず、
5人のメンバーでやることになった。
午後の早い時間に東京へ着いたので、新国立美術館でエルミタージュ美術館展へ行く。

マチスの「赤い部屋」を観てしまうと、約束の時間にはまだ時間があった。
歩こうか、と家内が言うので西麻布を抜けて渋谷まで歩く。
会場のスペイン料理レストランには少し早く着いた。
店が開いていなかったので、外で待っていると、
通りの向こうから金髪のKさんがやってきた。
彼女は、京都から来てくれた。
現在は書家として、レストランや料亭の筆文字ロゴを書いている。
NHKドラマの「ええにょぼ」などテレビの筆文字タイトルなんかも彼女の仕事だ。
間もなくTさんとIさんが、やってきた。
Tさんは、宇都宮で石のオブジェなどを創作している。
Iさんは、渋谷でデザイン事務所を立ち上げている。
このメンバーは個々に会うことはあったが、全員で会うのは初めてだった。
シャンパンで乾杯。
〈Kさんと家内だけ写真使用の許可が下りました〉
みんな、何を話していいか分からない。
36年ぶりだね、という言葉を何度も繰り返している。
何かきっかけがあれば記憶の糸がほぐれるのだろう、と思っていたが、
盛り上がるような昔話にはならず、みんな静かにワインを飲んでいる。
こういう感じ、どこかで見たことがあると思っていた。
「再会の時」というアメリカ映画だ。

60年代後半のアメリカのヒッピームーブメントの只中にいた仲間たちが、
友人の葬式で再会し、週末を過ごすという作品だ。
それにしても、僕と家内以外は、みんなつつましやかにしている。
熱い話をするには、もう少し時間が必要なのか、
それとも時間がたちすぎて、
振り返るべき過去なんてどうでもよくなってしまったのだろうか。
渋谷から西麻布へ流れた二次会でも、その空気は変わらなかった。
やがてシモンの話になった。
20年ほど前、シモンがTさんのいる宇都宮に会いに来たという。
長野のコミューンに行く途中で宇都宮に寄ったらしいが、
それ以来、連絡が途絶えたままであると。
シモンの話は、それ以上続かなかった。
夜更けの西麻布を5人で歩きながら、
近々、みんなで会おうという話をして僕たちは別れた。
米軍ハウスで一緒に暮らしていた岡本一生の歌を貼り付けます。
タグ:同窓会 岡本一生 シモン



